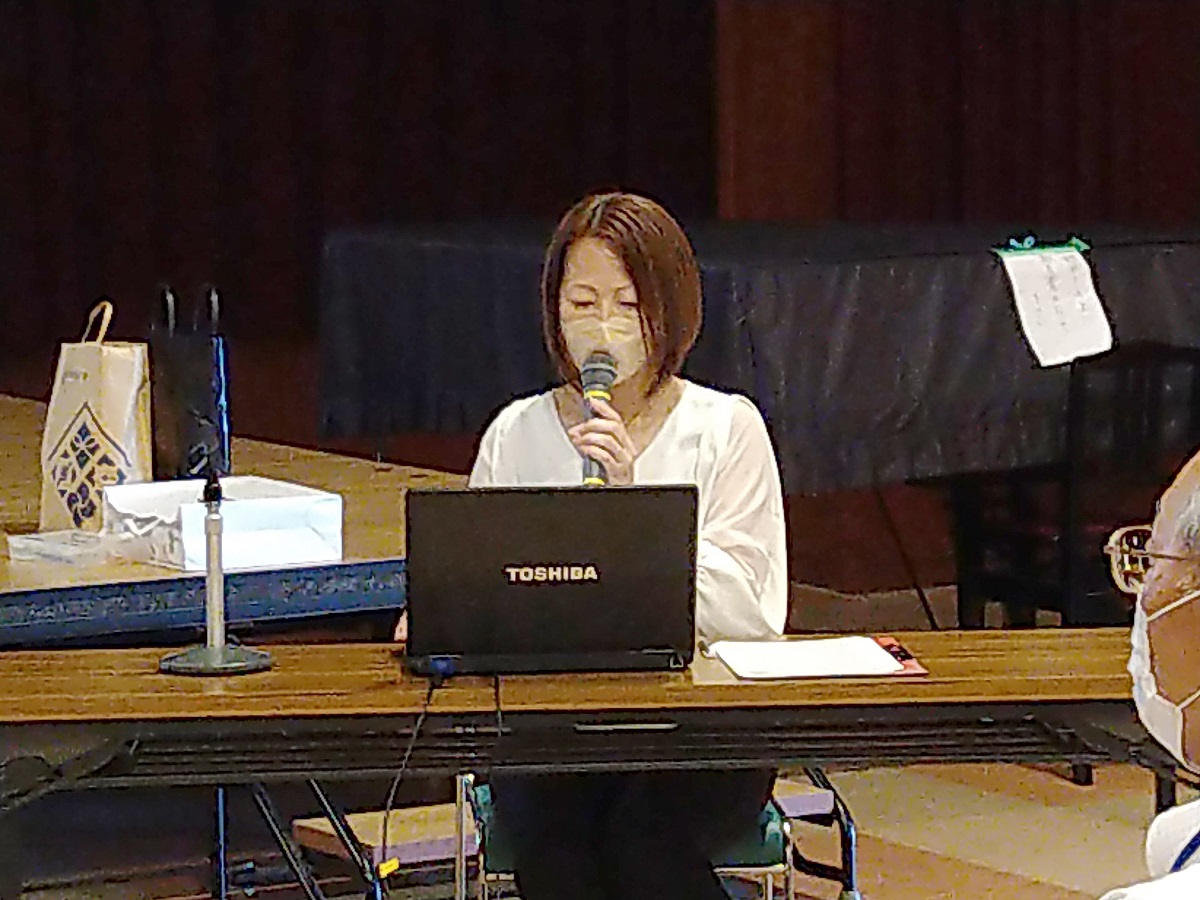令和5年度第1回 福祉推進員等懇談会の開催(ご報告)
毎回、福祉推進員及び民生児童委員等が一堂に会して開催の標記懇談会につきまして、次のとおり結果概要をご報告します。
令和5年度第1回 福祉推進員等懇談会 結果概要
令和5年5月 津沢地区社会福祉協議会
1.日 時 令和5年5月21日(日)10:00~11:50
2.場 所 津沢コミュニティプラザ 多目的ホール
3.出席者 全34名(内訳 福祉推進員12,民生児童委員8,会長,副会長2,理事5,参与2,
参事1,団体1,事務2)
(欠席者) 全24名(内訳 福祉推進員14,民生児童委員1,理事1,監事2,参事1,団体5)
4.配布資料
次第、講演資料:福祉推進員の役割について(市社協)及び津沢地区福祉推進員の名簿(R5.4.1~R7.3.31津沢社協)
5.結果概要
(1)開会(交流推進部会長)
(2)開会挨拶
会長から、開会の挨拶があった。
(3)懇談(進行:交流推進部会長)
最初に、進行から講演講師のプロフィール紹介があった。
第1部 講演「福祉推進員の役割について」
講師:小矢部市社会福祉協議会 総務地域課 杉谷誉志子氏
講師から、パワーポイント及び配布資料に基づき、次の説明があった後、最後に見守り中に「あれっ?普段と違う」と感じた場合には、民生児童委員と連携して対応願いたい旨の依頼があった。
(説明概要)
・「福祉」とは・・・ふつうに くらせる しあわせ
・「ふつう」の暮らしって?・・入浴、旅行など、人それぞれに「ふつう」がある。
・社会の変化①・・人口減少・少子高齢社会、世帯構造の変化、隣近所との関係の 希薄化・孤立化
・社会の変化②・・課題の複雑化・複合化(8050問題・ダブルケア・ヤングケ アラーなど)、コロナがもたらした孤立や生活困窮
・福祉推進員の役割・・①福祉問題の発見・キャッチ、②必要な福祉情報の提供
・基本的な役割・・要援護者への日頃の見守り・相談、民生児童委員等との連絡。
・見守りの目的と方法・・目的:安否確認や困りごとの有無、関係機関への情報提供 や相談。方法:訪問、立ち話、買い物先及び電話での確認や行事・サロンへの誘い と会話など。
・「あれっ?普段と違う」と感じるサイン・・げんきがない・顔つきがいつもと違 う、痩せてきた、数日姿を見かけないなど。
・守秘義務について・・民生児童委員と同様に守秘義務に留意せよ。
質疑応答
Q1.同じことを30分毎に繰り返して言う人に対する行政の相談先を教示願いたい。
A1.まずは親族、重症と思われる場合は市健康福祉課地域包括支援センター)に相談 されたい。
Q2.福祉推進員制度の見直し(守秘義務遵守の規定化)を願いたい。
A2.他地区では、福祉推進員のなり手不足が深刻になってきているため、制度見直し が、この問題に拍車を掛けるように思われる。意見のあったことは上司に伝え検討 する。
Q3.困り事などの行政相談先が分からないので、資料で示していただきたい。
A3.内容によって行政相談先が違うため、まずは民生児童委員に相談されたい。同委員 は内容によって相談先を把握して頂いている。
第2部 班別懇談 テーマ「高齢者の見守りについて」
予め、1班9名4班の編成に割り振られて着座の出席者が、各班進行役(民生児童委員)の下、テーマなどについて活発な懇談が行われた結果、次の意見等があった。
※ 班別懇談結果の概要
・「ほのぼの福祉世帯カード」に登録されていない人への関わり方には、まず声掛け が必要であり、また情報収集策として近所の人に聞く、特に認知症の人には積極的 に聞くことが重要である。
・要援護者の緊急時対応用「もしもカード」設置の拡大方策には、市報配布の自治会 班長に協力依頼も有効である。
・新人の福祉推進員は、高齢者にどの様にして接す(見守り)れば良いか悩んでい る。訪問時のほか、道で会った時や畑作業時には声を掛けるなどを行い、徐々に信 頼を深めて行くことが大事である。
・見守り時に要援護のサインを見逃さずに心がけ、有事には民生児童委員と福祉推進 員の緊密な連携が必要である。
【まとめ】(杉谷講師)
・「ほのぼの福祉世帯カード」や「もしもカード」の相談は、市社協が対応してい る。
・要援護者の諸問題には、福祉推進員がひとりで抱え込まずに、行政機関をはじめ民 生児童委員や近隣住民など地域ぐるみで対応することが必要である。
(4)閉会挨拶
副会長から、開会の挨拶があった。
(5)閉会・撤収
以上
※スナップ写真